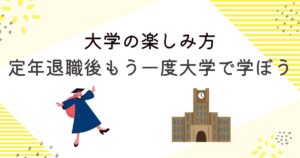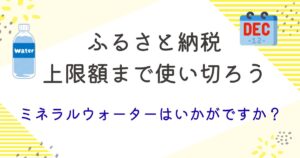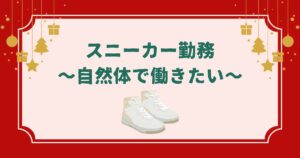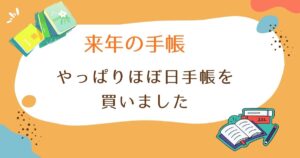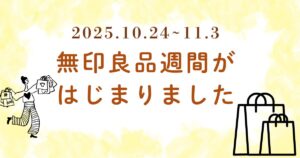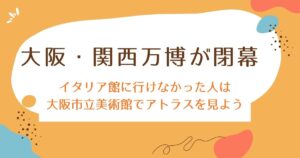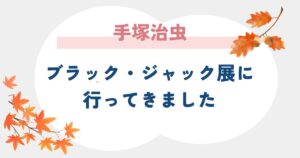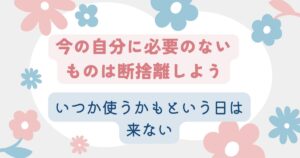先日スマホを忘れて帰るという事件がありました。
スマホはいつもデスクの決まった場所に置いていて、帰るときはそのまま鞄に入れます。
なぜ忘れたのかということをツラツラ考えてみると、
- その日は机の上を広く空ける必要があったので、いつもと違うところにスマホを置いていた。
- 普段は書類を置いている場所だったので、スマホの上に無意識に紙を置いてしまい、結果的にスマホが視界から消ていた。
- 帰るのが遅くなっていたので、さっさと帰りたかった。
ここから得られる忘れ物をしないための教訓は、
- 置き場所を固定化する。
- 別の場所に置いた時はそのことを常に意識しておく。(見えるようにしておく)
- 帰るときには忘れ物がないか具体的に確認する。(電車の運転手がよくやってる指差しチェックのようなもの)
つまり無意識と意識の関係です。
よくある話で、家を出てから、「ガスを消したか?」とか「ストーブを消したか?」などが、ふと気になる時ってありますよね。不安でたまらなくなって確認しに帰ったことがあります。
しかし大抵の場合はちゃんと消されています。
使い終わったら消すというのが習慣になっていると、手が覚えていて、スイッチを消すところまでが一連の流れになっているのでしょう。逆に無意識なので、改めて「本当に消したのか?」という不安に襲われても覚えておらず、「絶対に消した」という確信を持てないのかもしれません。
予防のためには、家を出る前に指差し確認ではないですが、「ガスOK」、「電気OK」など、動作を伴う行為をすることによって、「確認を顕在化させる」ことが効果的ではないでしょうか。そうすると「本当に消した?」という不安はなくなると思います。
ある行為を習慣的にやっていると無意識化されます。ですのでアクシデントが起きないようなシステムを構築して、その都度意識的に確認するということで、忘れ物を防げるようになるのではないでしょうか。
また無意識にやっていることにふと「違和感」を感じることがあります。例えばいつも持っているバッグが今日はなんだか軽いと感じたら、何かを入れ忘れている可能性があります。バッグを持った時の感覚が記憶されているので、違和感を感じて、「何か忘れてないか?」という信号を発してくれるのだと思います。この違和感を敏感にキャッチしたいです。
アクシデントは幾つかの些細なミスが重なったときに発生する確率が高いです。
ですので、「リスクの発生確率を低下させるシステムをあらかじめ構築しておくこと」、「もし何かが起こっても大事に至らないようリスク分担しておくこと」、「代替手段を常に考えておくこと」などがポイントだと思います。例えば皆が同じ行動をとらないとか、バックアップを二重三重に取っておくとか、電車が止まった時のルートを考えておくなどの対策です。
スマホにしても、今回は会社に忘れたので事なきを得たのですが、どこでなくしたのかわからないという場合、「iphoneを探す」のようなシステムを活用する方法があります。しかし「iphoneを探す」を利用するためには事前の設定が必要です。いざ使おうと思っても例えば位置情報が無効になっていて使えなかったなどにならないようにしたいです。
ミスやアクシデントは起こるものだという前提の上、いろいろな対策を考えておくというのが大原則です。
このあたりのさじ加減は自分のリスク許容度にもよるのですが、(過剰に心配する必要なありませんが)、後で後悔しないよう、所謂「空振りに終わってもいい」くらいで考えておくが精神衛生上いいかもしれませんね。