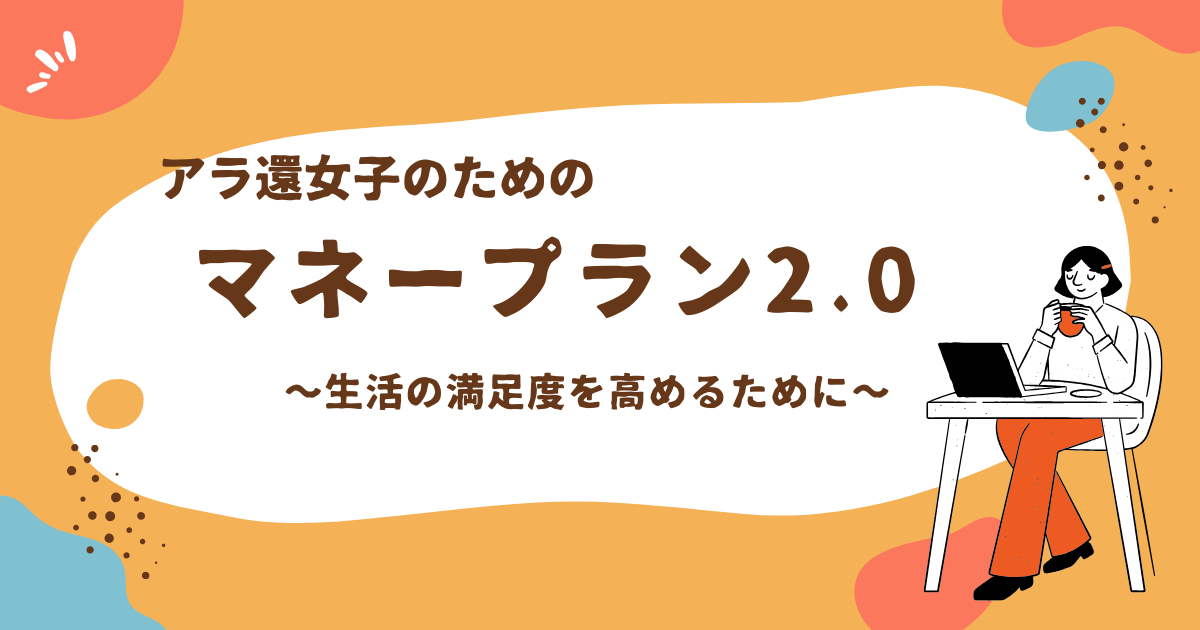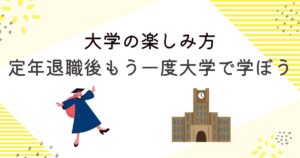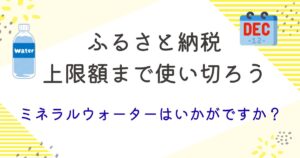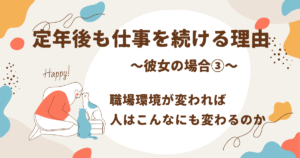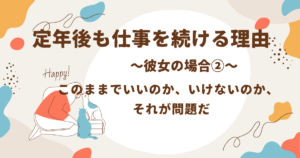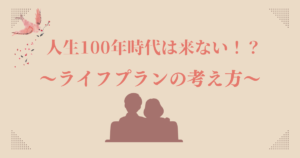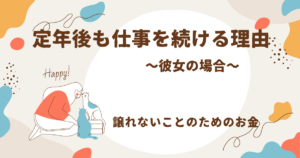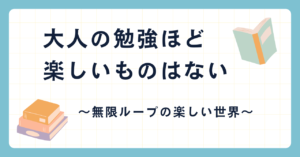生活の満足度を高めるために、マネープランをアップデートしよう!
この年度末で60歳の定年を迎える人も多いでしょう。
最近は65歳くらいまで働くのは普通になっているので、世間一般の定年のイメージは65歳なのかもしれません。しかし、60歳を超えると働き方も変わるでしょうし、60歳がひとつの節目の年であることには間違いありません。
もしあなたが60歳を超えて働き続けていて1年なり2年経ったとするならば、もう一度、今の時点で今後のことについて見直してみませんか。
今や定年後の生活がリアルにわかるようになっているはずです。定年前に想像していたイメージと異なっているかもしれません。考え方も変化しているかもしれません。
当面65歳を視野に入れて、このままの状態を続けるのかそうでないのか考えてみるのはいかがでしょう。
現況はどうでしょう
・再雇用で働いているが、仕事が全く面白くない。
・職場の人間関係がストレスだ。
・起業したけど売り上げがゼロのままだ。いつまで続けようか。
・こんなに物価が上がるとは思わなかった。もっと働かないといけない。
・まだまだ元気だし70歳までは働きたいと思っている。
・やりたいことが沢山あるので、働く時間をもう少し減らしたい。
・65歳までは働くが、そこでキッパリ仕事は辞める。
・起業して絶好調だ・・・ ・・・。
状況の変化に伴いスタンスも変わります。
何を重視するかという価値観によってもスタンスは変わります。
何はともあれ、ベースとなるマネープランを再確認しておきましょう。
マネープランの考え方は年齢に関係なく基本的に同じです。
つまり、必要なお金を何らかの手段でカバーすることです。
定年女子の場合であれば、破綻しないためには、下記の式が成立することが必要です。
今後必要なお金 ≦ (勤労所得+年金) + 貯蓄
*簡略化のため、働いて得る収入のみを考え、家賃収入や配当等は考えていません。
左辺の「今後必要なお金」は過大に見積もる必要はありませんが、若干の余裕を見ておいた方がいいでしょう。この先、物価がもっと上がるかもしれません。と言って生活のレベルを下げるのも考えものです。贅沢する必要はないですが、自分が満足できるレベルはキープしたいです。
右辺の「年金」は一生涯もらえます。何歳からもらうかによっても額が変わるので、他の所得との兼ね合いも重要です。70歳からだと42%増、75歳からだと84%増です。
「勤労所得」はいつかゼロになるでしょう。(生涯現役の人は別ですが)
「貯蓄」も運用しつつ取り崩し、最後はゼロを目指しましょう。必要以上にため込んでもしょうがないです。使い切ることを考えましょう。(あくまで私の意見です)
この式を睨みながら今後のプランを考えます。
取り敢えず100歳まで生きるとして、お金の流れから大まかに3つの期間に分けて考えてみましょう。(年金開始の時期は自分で選べますし、貯蓄額も人それぞれでしょうから適宜アレンジしましょう。)
1 定年退職~年金をもらえるまで 勤労所得+貯蓄
2 年金をもらいながら働く期間 年金+勤労所得+貯蓄
3 年金のみの期間 年金+貯蓄
1の期間は、働いてフロー収入を得る必要があります。(貯蓄が十分なら経済的な理由で働く必要はありませんが、なかなかそうもいかないのではないでしょうか。今や60~64歳の男性で84.4%、65~69歳 で61.6%、女性の場合は60~64歳で63.8%、65~69歳で43.1%が働いています。)(R6高齢社会白書より)
2の期間は年金をもらいながら働く期間です。働く理由は経済的な理由だけではないですが、ここでは取り敢えず経済面だけを考えます。
年金だけだと不足であれば、年金+α をめざします。
例えば月10万円ならば下記のようなイメージです。
時給1,000円で1日6時間 週4日働くと 96,000円です。
また、働かずに資産を取り崩すとしたら
NISA満額の1,800万円を3%で運用しながら毎月10万取り崩しても20年以上持ちます。
3の期間はもはや働かず、年金で足りない分は資産の取り崩しで対応します。でも年齢を重ねると、おそらくそんなにお金を使わないような気がします。
ここまで整理して、破綻しない見込みならば、次のステップへ進みましょう。
そうです。やりたいことをどんどんやりましょう。
健康な時には限りがあります。お金を持っては死ねません。
最終的には、お金と自由に使える時間のバランスを取りながら、生活の満足度を上げていくことに帰着するのだと思います。
今の状態を続けるのか、何かを変えるのか、何かをやめるのか。
確信をもって次のステップに進むために、マネープランを常にアップデートすることを意識したいです。
そして誰憚ることなく、自分の満足度の最適化をめざしましょう。