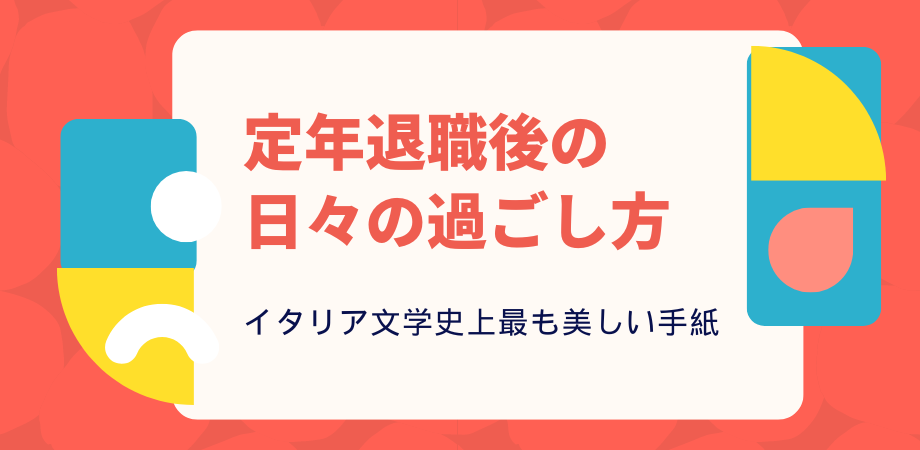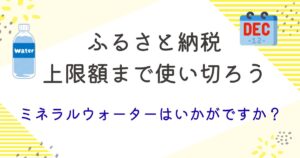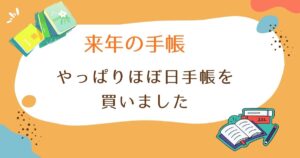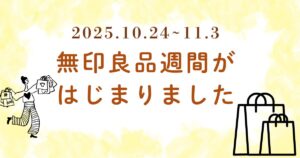先日、たまたま休日出勤が続いたことがありました。
ひとつは朝から半日出勤、もうひとつは昼から半日出勤、どちらも半日ですが、どちらがいいのかとふと考えてみました。
朝から出勤の場合は、いつもの日と変わらないルーティンで出勤します。
休日の朝から出かけていくのはちょっと嫌だけど、一旦家を出てしまえば半日仕事なので、それほど負担は感じません。午前中に仕事を終えると、例えば休日の朝に所要を終えた感じで、後は通常の休日です。ですので休日感はあります。
逆に昼から出勤の場合は、家を出る時間は確かにゆっくりですが、帰ってくる時間が普段と同じなので、そこから何かやろうという気が起きません。となると、出かけるまでが勝負で、この間に全部済ませてしまおうとしてしまいます。
例えば12時に家を出るとして、それまでの間に、洗濯や掃除、買い物、あるいはジムに行くなど、いつも休日にやっていることを全部済ませておこうと思う訳です。時間の制約があるからか、結構集中してできます。逆にいつもより早起きしてでも半日で済ませてしまおうと思います。タイムリミットがあるだけで効率はものすごく上がります。しかし、やることはやったとはいえ、所謂休日感というものはありません。
一長一短なんですが、結論としては朝から仕事に行く方が休んだ感があって楽な気がします。
そして、休日であれ何であれ半日出勤というのは余裕があると感じます。
かつてケインズは、100年後には1日3時間も働けば生活に必要なものを得ることができるようになるだろうと予測しましたが、(「われわれの孫たちの経済的可能性」(1930))、残念ながら現実は全然そうはなってはいません。
AIが進化しても、とってかわられる仕事はあったとしても、多分新しい仕事やブルシット・ジョブは増えるんだろうなと思いつつ、やっぱり4時間から6時間程度というのが理想だと思ったりします。

さて、イタリア文学史上最も有名で美しいと言われているマキアヴェッリの手紙があります。
塩野七生の「わが友マキアヴェッリ」の序章にもでてくるので読んだことがある人も多いでしょう。
ロレンツィオ・デ・メディチの下でのルネサンス最盛期を迎えたフィレンツェは、ロレンツィオの死後、メディチ家の追放、サヴォナローラの神政と失脚という激動の時代が続きます。
そのような中、マキアヴェッリは1498年にソデリーニ政権下でフィレンツェ共和国の書記官に選出され多忙な日々を送っていましたが、1512年、メディチ家の復帰とともに職を解かれてしまいます。加えて、メディチ家暗殺の陰謀に巻き込まれ逮捕、その後、大赦で釈放されますが、以後フィレンツェ近郊の山荘に移り住み隠遁生活を余儀なくされます。
その当時の日々を綴ったのがこの手紙で、1513年12月10日にフランチェスコ・ヴェットーリ(法王庁にフィレンツェから派遣されていた大使)に宛てたものです。
マキアヴェッリは時に43歳。
手紙によると、朝は日の出とともに起きて、森で樹を切らせたりして働く。泉のほとりでしばし読書に勤しみ、居酒屋へ行き人と話し、家に帰って昼食をとる。その後は夜まで居酒屋で賭け事をして過ごすとあります。そして、
夜がくると、家にもどる。そして書斎に入る。入る前に、泥やなにかで汚れた毎日の服を脱ぎ、官服を身に着ける。
礼儀をわきまえた服装に身をととのえてから、古の宮廷に参上する。そこでは、わたしは、彼らから親切にむかえられ、あの食物、わたしだけのための、そのためにわたしは生をうけた、食物を食すのだ。そこでのわたしは、恥ずかしがりもせずに彼らと話し、彼らの行為の理由をたずねる。彼らも、人間らしさをあらわにして答えてくれる。
四時間というもの、まったくたいくつを感じない。すべての苦悩は忘れ、貧乏も怖れなくなり、死への恐怖も感じなくなる。彼らの世界に、全身全霊で移り棲んでしまうからだ。
塩野七生「わが友マキアヴェッリ」
かくして君主論が著されていくわけですが、本当に涙が出る程美しい手紙です。
7人家族だったそうです。山荘には畑もあり、オリーブや葡萄酒も産したでしょうから、贅沢をしなければ暮らしてはいけたのでしょう。
しかし、
根っからの都市生活者で、つい先頃まで国政の中枢にいた人間にとっては、山荘での静かな生活は、耐えがたいくらいの生との断絶を意味する。これが、44歳に移ろうとするマキアヴェッリを、苦しめずにおかなかったであろう。
ニコロ・マキアヴェッリは、平穏な隠遁生活を、それはそれとして愉しめる男ではなかった。これも第二の人生と、悠然とかまえる性質の男でもなかった。彼は、胸中に怒りをたぎらせながら「隠遁」したのである。「君主論」は、この怒りの産物であったと思うのは、誤った判断であろうか。
塩野七生「わが友マキアヴェッリ」
43歳での山荘暮らしに心中を察するに余りある状況ですが、
それだけにこの手紙は何度読んでも美しいのです。
ちなみに君主論が評価されるのはずっと後の18世紀になってからです。