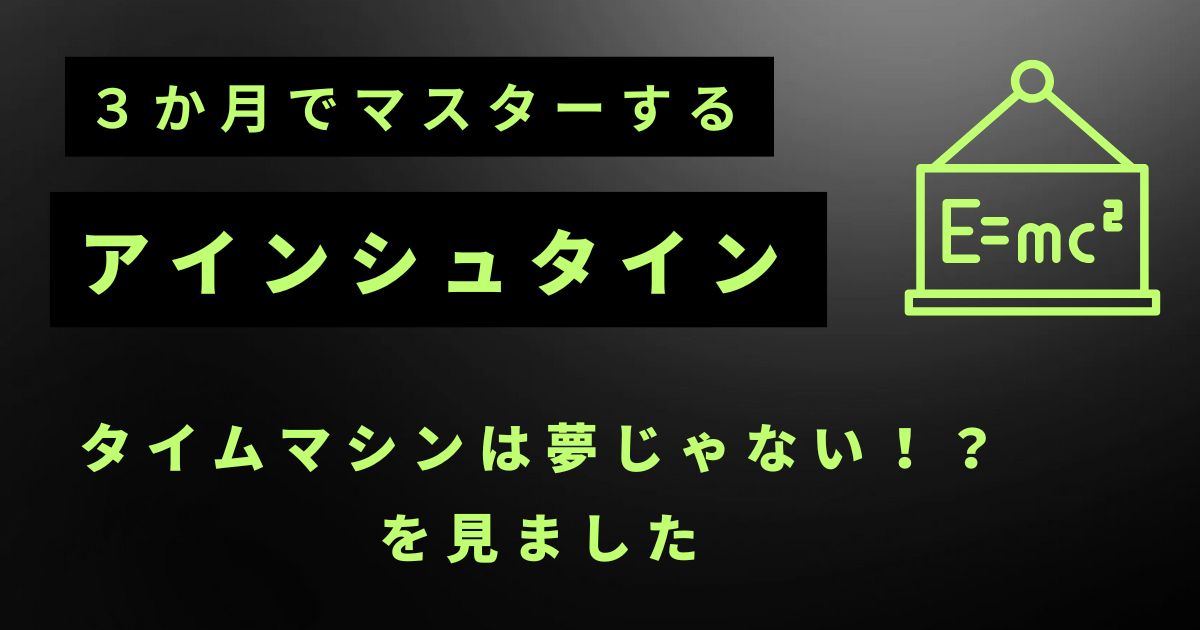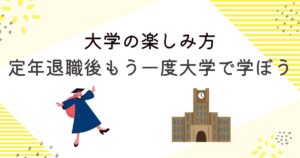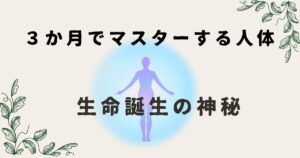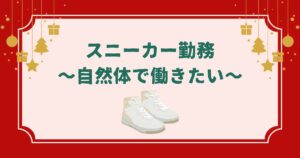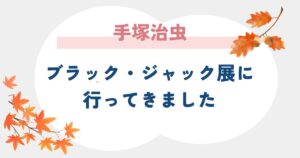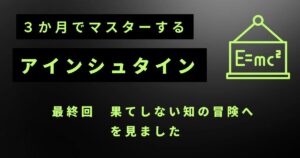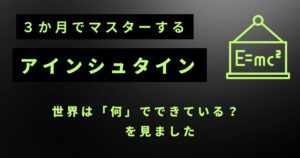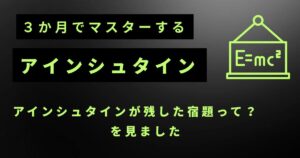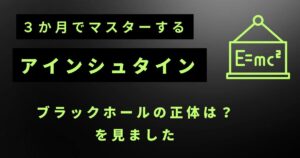3ヶ月でマスターするアインシュタイン、第3回のテーマは「 タイムマシンは夢じゃない!?」です。
光の速さは一定という「光速不変の原理」をもとに、動いている観測者にとって光の速さが変わらないためには時間と空間が変化しないといけないという前回の内容を受け、今回の放送は、
「動いているものの時間は遅くなる」
「動いているものの長さは縮んで見える」
ということの、実演を交えながらのわかりやすい説明でした。
特に面白かったのが「動いているものの時間は遅くなる」という話です。
アインシュタインが思考実験で用いた仮想的な時計「光時計」が登場します。
一方(下部)に光源があり、そこから放たれた光が反対側(上部)に設置した鏡に反射して元の場所に戻ってくるのに、例えば1秒かかるとします。
静止している観測者から見ると、光は1秒で上下に往復します。
ところがこの光時計を電車に乗せると、電車とともに時計も動くので、電車の外にいる観測者から見ると、光は上下の往復ではなく、進行方向側に向かって斜め上に進み、斜め下に戻ってくるように見えるわけです。
さて、速さ=距離÷時間 です。そして光の速さは一定です。
ですので、光の速さが一定であるためには距離が長くなったら時間も長くならないといけません。見る人の立場によって時間が変わるのです。
動いている人と静止している人の時間の流れが異なる例として、ほぼ光速ロケット(番組で紹介されていたのは光速の99%の速さ)に乗っている人と地球にいる人とでは、計算上、時間の流れの差が7倍になるという話が紹介されました。
ほぼ光速のロケットに乗っていた人の1年は地球にいた人の7年に相当するということです。地球に帰ってきたら周りの世界は7年進んでいる、つまり、7年後の未来にいるということになるのです。
まさに、竜宮城から帰ってきた浦島太郎ではありませんか。
タイムマシンというと時空を超えて過去と未来を行ったり来たりできるイメージがありますが、残念ながら過去にはいけないようですし、一方通行で元には戻れないようです。過去に行けたとしても、「親殺しのパラドックス」など過去の何かに影響を与えると因果律で現在が狂うという話、よくありますよね。
さて、未来の世界に行くというのはどうなのだろうと妄想が広がります。
例えば7年先の未来では、周りの人が自分より7つ年を取っているということです。
仮に自分の子供が中学3年生だったとしたら大学卒業の年になっているわけで、結構衝撃的です。
それでは30年とか50年とか100年だったらどうでしょう。
30年はワンジェネレーションですので、自分の子供が自分より年上になっているかもしれないし、同い年だった友人が親ぐらいの年齢になっていたりします。これは結構辛いです。50年先だったら祖父母くらいの年齢です。もし100年だったら、知った人はいないでしょう。
中途半端に知っている人が年を取ってしまうより、誰も知った人がいない世界の方がまだ諦めがつくのかもしませんが。。。
未来に行けるとしても必ずしも素晴らしいことだとは限らない気がしました。
という妄想が広がった第3回の放送でした。