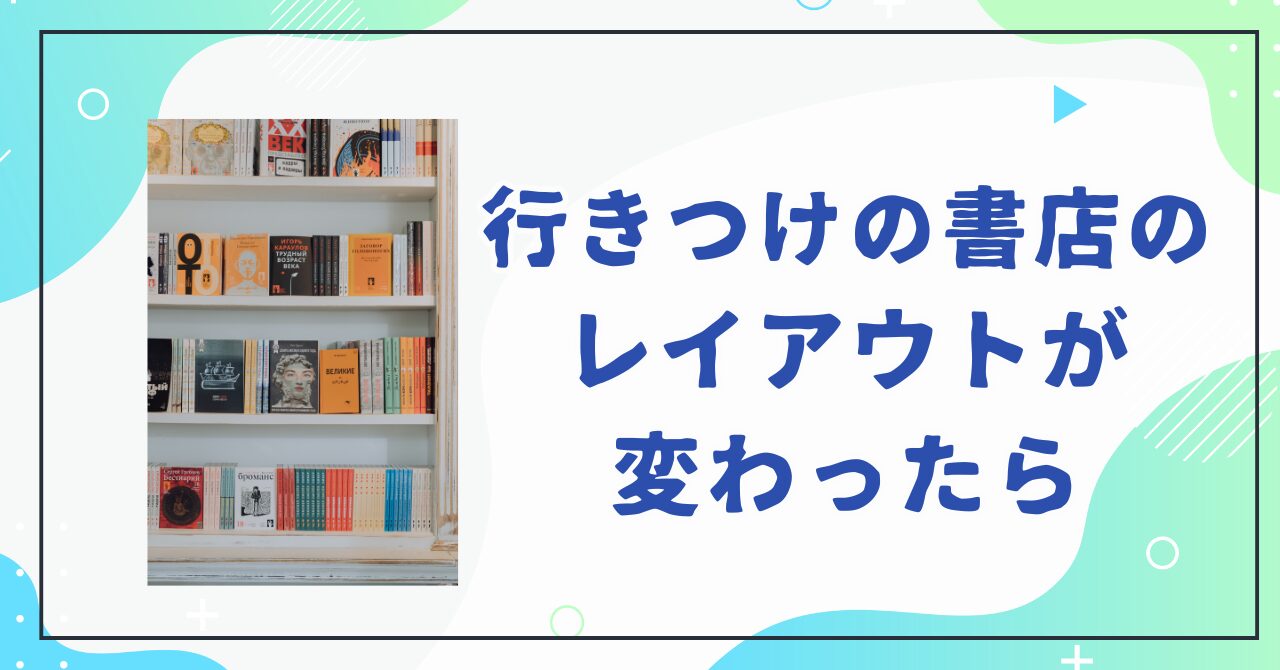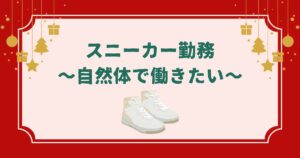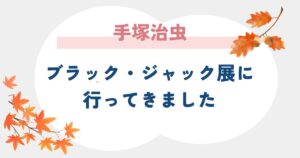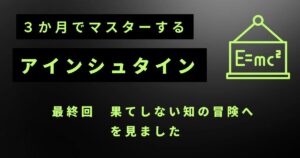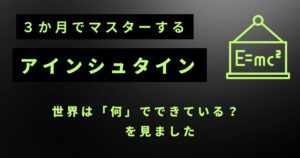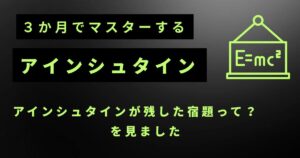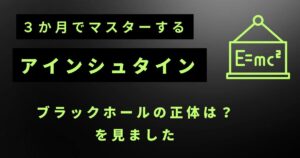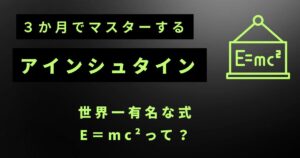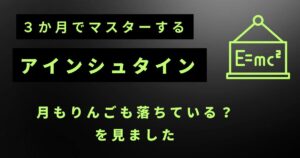書店に行く時は大型店を選びます。
何故なら品揃えが豊富だからです。
漠然と、この分野にどんな本があるのかを探しに行く時は超大型店が最適です。
加えて関連本や予期せぬ本に出会う楽しみもあります。目当ての棚に行くまでの間に思いがけない本に出会って、衝動買いしてしまうことも多々あります。
指名買いであればアマゾンでもいいのですが、それでもやっぱり買う前に現物をパラパラと捲ってみたいわけです。
アマゾンの「サンプルを読む」と「現物」ではやっぱり違うように感じます。現物を眺めて「予想通り面白そうだ」とか、逆に、「こんな内容だったら買うまでもない」とか判断します。ですので現物を見る目的で行く場合は、在庫の検索をして、現物があることを確認してから出かけます。
紙の本か電子書籍かの選択は本の読み方によります。
ページを行ったり来たりしながら読む本や、書き込んだり、図版を参照しながら読みたい場合は紙の方が便利です。
他方、さらっと流すような本は電子でもいいのかなと思います。
分厚い本や、高い本などは電子にするかどうかちょっと迷います。急いでいる時や、在庫がない時、電子版しかない場合には、消去法的に電子になりますし、飛行機で読むのは迷わず電子です。
さて、よく行く本屋が何軒かあります。
家の近くの書店、会社の近くの書店、駅の近くの書店、定期的に通っている場所の近くにある書店、わざわざ出かけていく大型書店などですが、それぞれ店舗によって品揃えや強い分野に違いがあり、適宜使い分けています。
いずれにしても、よく行く店はレイアウトが頭に入っているので、こういう本はこの辺りにあるはずという暗黙の了解のもとで店内を歩きますし、頻繁にその店の棚を眺めているので、新刊本など変化があればすぐに気が付きます。
他方、初めて行く本屋では、自分の得意分野の棚の品揃えを見渡すと、自分に取ってどの程度活用できる店なのかが直感的にわかります。「こんなマニアックな本がある」とか、「品揃えがイマイチだ」とか、勝手な値踏みをしたりしてしまいます。
さて、このほど家の近くの本屋のレイアウトが変わりました。
マイナーチェンジではなく、結構ドラスティックに変わっていて、正直、戸惑いました。動線が完全に変わります。
ここにあるはずという棚が棚ごと移動していて、一瞬、「この分野の取り扱いがなくなったのか」と焦ったり、「そんなはずはない」と探すと、ものすごく離れた場所に置かれていたり、そもそも慣れていないから店内をうろうろするだけでも違和感があります。
目先が変わるという意味で、レイアウト変更は時々あってもいいのかもしれません。
まあ、それでも、実際2~3回行ったら慣れてしまいました。
人は簡単に慣れてしまうのだと今更ながら思ったところです。