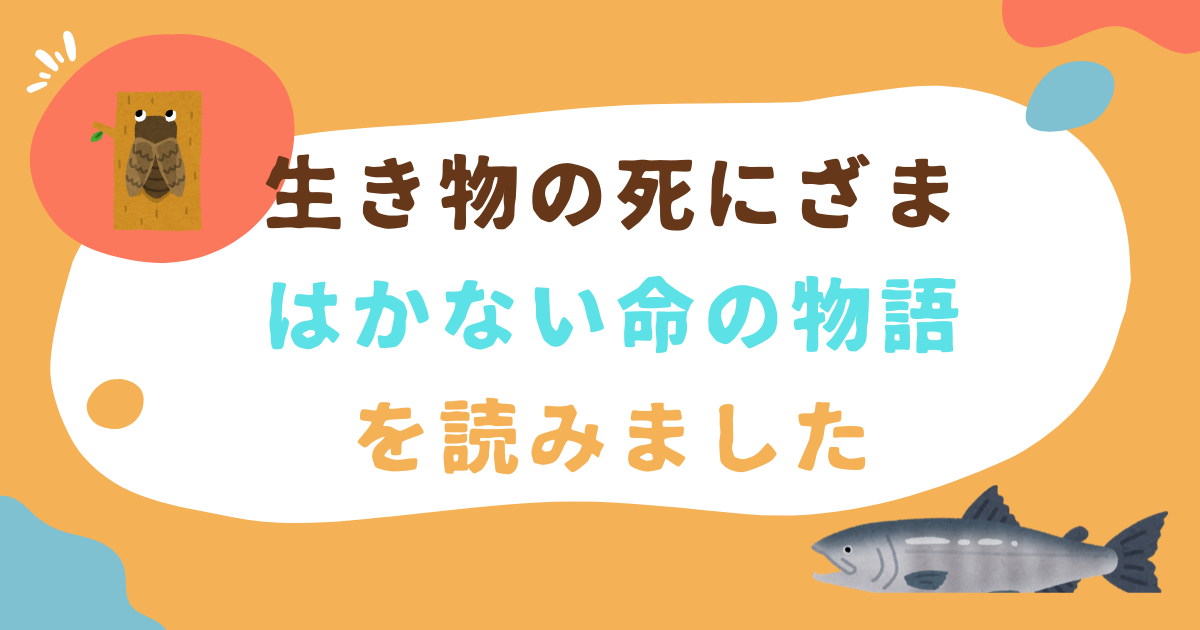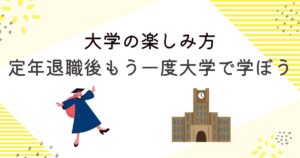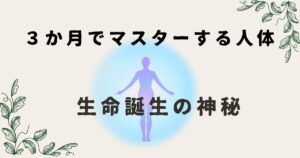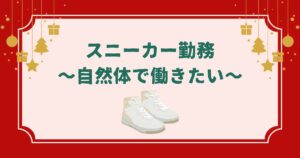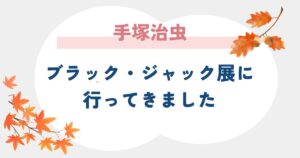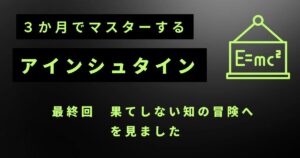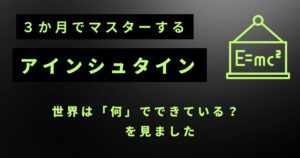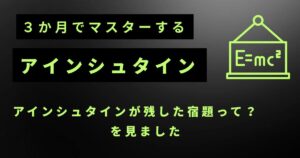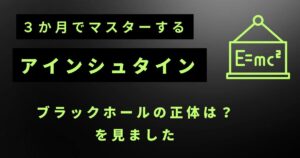稲垣栄洋さんの「生き物の死にざま はかない命の物語」(2020年)を読みました。
何年か前に話題になったベストセラー「生き物の死にざま」の姉妹編です。
前著の「生き物の死にざま」は大分前に読んだのですが、本の帯に書かれているとおり
“「命のバトン」をつなぐために” 生き物たちが織り成す29の物語が抒情的に語られます。
セミ、サケ、カマキリ、タコ、ウミガメ、ゾウなどのお話です。
例えばセミは土の中で7年程過ごします。そして地上に出て成虫になり、求愛、交尾し、夏の終わりには力尽きて死んでいくのです。
遠く離れた海の中から生まれ故郷の川に帰ってくるサケ、河口から川に入るともはや餌を食べることもなく、ボロボロになりながらひたすら上流を目指し、到着したら、パートナーを選び、繁殖行為を行う。そして、それが終わると息絶えるのです。
他にも、
卵が孵るまで飲まず食わずの状態で見守る母親若しくは父親
子が生まれてきたら自らの肉体を食べ物として差し出す母親
栄養のためにオスを食うメス・・・
子を残すための壮絶なドラマが繰り広げられます。
そしてこの営みは繰り返されるのです。
この本の中に何度も出て来るフレーズ 「そういう風にプログラムされている」
動物には意識はないと言われています。時間感覚もないでしょうし、死の観念もないのでしょう。
そうじゃなかったら怖くて子どもなんか残せないのではないでしょうか。
サケやウミガメだって戻ってこないかもしれないと思ったりします。
逆に言えば、時間や死を意識するヒトが見ているからドラマを感じるのでしょうが、
それでも心を揺り動かされる切ないストーリーであることに変わりはありません。
そして先頃遅ればせながら読んだのが、姉妹編の「生き物の死にざま はかない命の物語」です。
第1章の「愛か、本能か」では、コウテイペンギン、恐竜、毒クモ、ゴリラ、チーターなどの命のバトンをつなぐ営みが語られます。主人公は変われども、前作と同じようなテイストで書かれていくのか思いきや、第2章以降雰囲気が一変します。
「生き物と人」(第2章)、「節理と残酷」(第3章)、「生命の神秘」(第4章)という章立てに従って、それぞれの物語が展開されます。
親が生んだ木の根元の土の中で何年も暮らし大人になるセミ、鳥などの天敵を避け、まだ暗いうちに木を這い上がり羽化するはずなのですが・・・、土の中にいる間に周囲の環境が変わってしまうことがあるのです。例えば木が切られていたり、土がコンクリートで埋められたりしてしまっている。あきらめてアスファルトの上で羽化するセミもいるそうです。羽化をはばまれた夏というタイトルが痛々しい・・・
我々が何気なく食べるシラス丼、シラスはイワシのこどもです。
西日本の海で生まれ、黒潮に乗ってはるばる東北までやってきて、再び南下していきます。しかし、イワシには天敵が多く天寿を全うするのは難しいのです。
いつ襲われるかわからない。いつ食べられるか分からない。常に誰かに襲われて食べられるかもしれないという恐怖。そんな恐怖の中でイワシは生きている。
明日はないかもしれない。明日はいないかもしれない。
生きていくということは、そういうことなのだ。
シラスとイワシ 大回遊の末にたどりついたどんぶり より
他にも
モズに串刺しにされるカエル
病原性の糸状菌に冒されて水分を奪われ干からびてしまったバッタ
鳥の体に中に移動したい寄生虫に操られ、葉の上で鳥に食べられてしまうカタツムリ
死後、深い海の底にゆっくりゆっくりと沈み、自らの身体を他の生物に捧げ、海の生命の循環に溶け込む巨大なクジラ
巨木になればもっと長く生きられたかもしれないのに短い命を選ぶ雑草
物語は続いていきます。
そして、最後に人間が登場します。
未来のことがわからない生物は今を生きていますが、人間は未来を想像することができるし、死も想像できるのです。
人間として生まれてきた以上、今を生きることはとても難しい。
二度と来ない過去や、未来のことを考えないわけにはいかない。
私たちは、なんというやっかいな生き物に生まれてきてしまったのだろう。
人間 ヒト以外の生き物はみな、「今」を生きている より
あなたの死にざまは、どのようなものなのだろう
という問いかけでこの本は終わります。
前作と読後感が全く異なりますが、いろいろなことを考えさせてくれる本です。