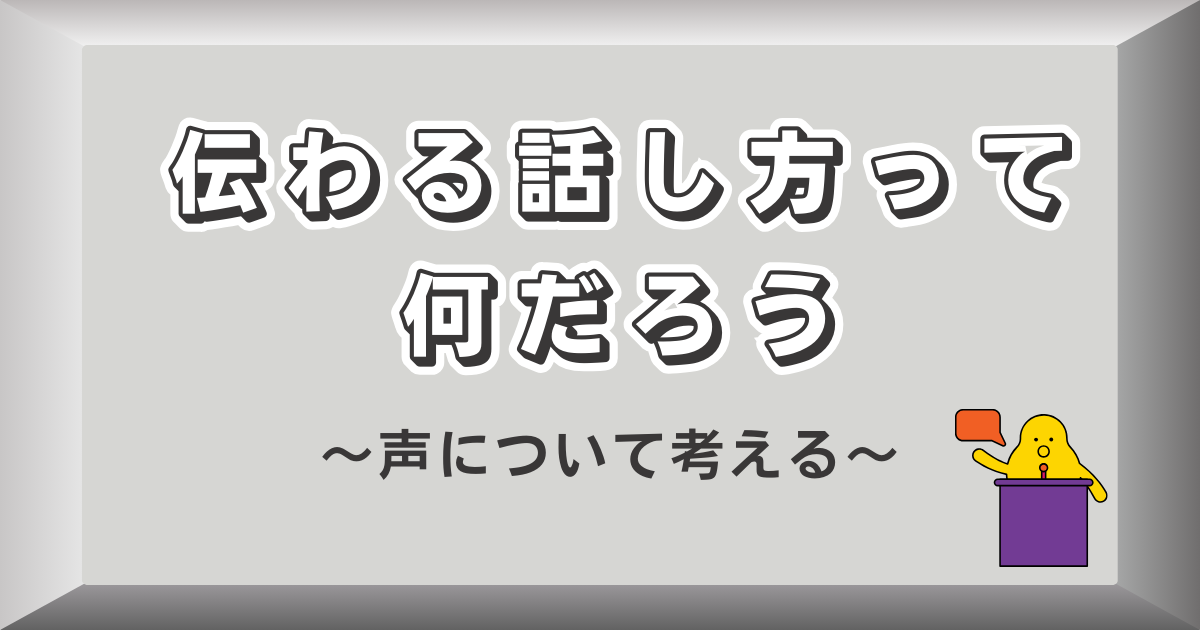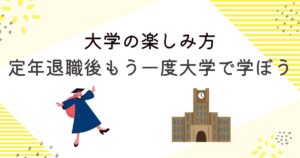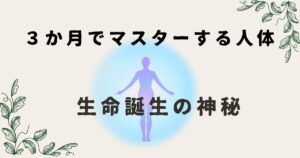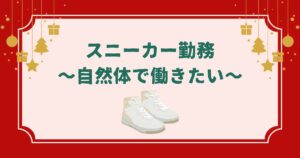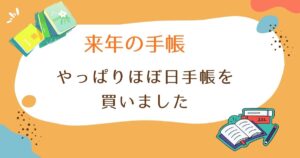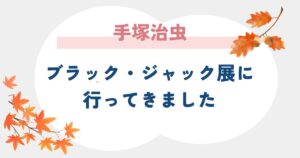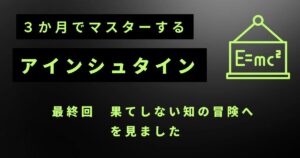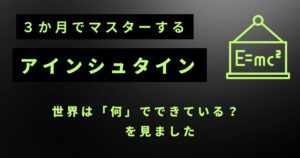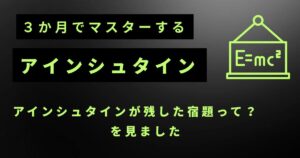自分が完全に聴く立場にある時、―例えば講演会やセミナーに聴衆のひとりとして参加した場合などー、スピーカーの話し方をシビアに観察していますよね。
そもそも講演会やセミナーは、話を聴きたくて主体的に参加するので、聴こうという意識は高いはずです。
少々喋り方が下手であっても、早口であっても、滑舌が悪くても、一生懸命聴こうとするのではないでしょうか。
(いやいや動員されたなどの場合はもっとシビアです。面白くなければ即、脱落します。)
特に関心がないスピーチ、例えば社長の訓示(?)だとか来賓挨拶などは、内容が面白ければフムフムと聞くし、表面的な話だとすぐに興味を失ってしまいます。聞いた傍から忘れていく典型的なパターンです。
コミュニケーションには、視覚情報、聴覚情報、言語情報の3つの情報があると言われています。昨今では「見た目が9割」などの言葉が人口に膾炙しているように、言語情報よりも「見た目」や「話し方」の方が重要という空気がある様に思います。
確かにすごくいい内容を話しているにも関わらず、見た目や話し方で損をしている人もいます。
「あの喋り方は生理的に嫌」などと言われてしまうと、どうしようもありません。
逆に、立て板に水の如く喋られても、中身がスカスカだったりすると、聴いてくれません。
また、正論を述べられても退屈してしまいます。かえって訥々とした喋り方の方に感動したりすることもあります。
事程左様に聴衆は移り気です。
まあ、自分が聴く側にいる時は、自分のことは棚に上げて、「こういう喋り方では伝わらないよね」とか「何言ってるのか全然分からない」とか、勝手なことを思っています。
そして、一旦喋り方や見た目が気になってしまうと、話の中身はまず入ってきません。「なんか言ってたよね」というくらいにしか覚えておらず、せいぜい、「自分が喋るときは気をつけよう」という教訓を得るのが唯一のメリットだったりします。
それでは、自分がいざ喋る側になったとき、どのくらい聴き手に伝わっているのでしょう。伝えるためにはどうしたらいいのでしょう。
自分のスピーチに自信満々という人はいいですが、通常は何かしら悩みを抱えているのではないでしょうか。そして、「伝わる話し方」とか「プレゼンの仕方」などの類の本に手を出したりするわけです。
そのような中、先日、墨屋那津子さんの “あなたの話が「伝わらない」のは声のせい” を読みました。
本の冒頭に声の「負の印象」診断というページがあります。
□「え?」と聞き返されることがある
□ 声が小さい・大きい
□ かすれる
□ うわずる
□ 早口
□ 話していて息が続かなくなる
□ 滑舌がよくない
□ よく聞き違いをされる
□ ビジネスの場などで、ふだんより少し高い声を出してる
□ ビジネスなどの場で、言葉を区切って話している
□ 怒っているように思われてしまう
□ 信頼関係の構築に時間がかかる
□ 言っても聞いてくれない
□ 棒読みだと言われる
□ アニメ声だと言われる
そして思い当たる人に向けて、それぞれの対処法が紹介されています。
この本を読んで「声」という点から、私が面白いなと思ったのは、以下のような箇所です。
滑舌を良くするためのアクショントレーニングというのは、言葉を発音するときに大きな動きを加えることで滑舌を改善する方法で、アクションが伴うと、言いにくかった言葉が発音しやすくなるというもの。なぜなら、体を動かしながらしゃべると呼吸の力を借りてエネルギッシュな声になるからとのことです。
これは、なかなか面白い。しかも、簡単にやってみることができます。本の中では「きゃりーぱみゅぱみゅ」が例に挙げられていました。
やまびこトレーニングは、
①目の前のパソコンに向かってヤッホーという
②部屋の中の壁などに向かってヤッホーという
③隣の部屋の棚に向かってヤッホーという
④窓の外の隣の家のベランダに向かってヤッホーという
というステップを踏んで、距離を意識して、距離にあった声を出すというトレーニングです。
これもなかなか面白いです。
他にも、直ぐにでも実践できるヒントが沢山詰まっています。
自分の声に自信がない人におススメです。